自動車の自動運転の話が持ち上がって久しい。世界中の自動車メーカーが自動運転に経営資源を投入し、目下、技術開発が進行中です。
欧州のプレミアムブランド、そして、日本車を含めて自動運転の先駆けとなる運転支援の技術が投入された車が発売されてきました。
2021年現在、「レベル1」そして「レベル2」の段階ながら、自動運転車の技術革新に夢が膨らみます。そして、2021年、レベル3を搭載したHONDAレジェンドが販売されました。
巷では、タクシーやトラックの自動運転化・・・なんて話が飛び交っているようです。
しかし、管理人はそのような話題に対して懐疑的。
完全な自動運転車である「レベル5」となると、現段階では五里霧中の世界で現実味がありません。
いつの時代もマスコミは情報を煽る傾向があります。
一例として2009年、三菱自動車が三菱i(アイ)にバッテリーとモーターを搭載した純粋なEVをリリースしました。そして、翌2010年、日産自動車がEV車のリーフを発売。
当時のマスコミ報道は、かなり暴走していました。
付和雷同的な大衆が多いのか、
「今後、ピストンエンジン車からEVへと一気に切り替わるのでは?」
なんて会話が聞こえてきました。
「EV化の流れに乗り遅れるな!」とばかりに、一部の中小企業がEV開発に乗り出していったのです。
そして2023年、日本、そして海外でEVの普及率はどうでしょう。
・お隣さんがEVに乗っていますか?
・タクシーやトラックがEV化しました?
・2022年、EV新車販売台数が全体の約80%を占めているノルウェーでEVの諸問題が噴出しているのをご存知ですか?
誰もが過去の出来事は簡単に見えるものの、未来は未知の世界。しかし、管理人は当時、別のブログでこのように呟いていました。
「ここ10年や20年でEVは普及しないよ。」
では、自動運転車の普及はどうかと言うと、EVと同様、
「ここ10年や20年でレベル5の自動運転車は普及しないよ。レベル5の実現は不可能に近い。」
タクシーやトラックのプロドライバーの方々は失業の心配が無いのでご安心ください。
自動運転の定義

日本政府は自動運転を以下のように定義しています。
レベル1
加速、ステアリング操作、制動のどれかをシステムが支援。一例:衝突被害軽減ブレーキ。
レベル2
システムが加速、ステアリング操作、制動のうち同時進行で複数を支援。一例:アダプティブクルーズコントロール。
レベル3
限定的な条件下でシステムが加速、ステアリング操作、制動を行い、状況によってシステムがドライバーに運転をバトンタッチ要請する。
レベル4
特定の状況下でシステムが加速、ステアリング操作、制動を全て行う。その状況が続く限りドライバーは運転に関与しない。
レベル5
無人運転。ドアtoドアで移動が可能。
人間の運転能力は超越している

とある情報源によると、自動運転の技術開発を進めれば進めるほど、次々と「壁」が立ちはだかり、一筋縄ではいかないようです。
運転免許証を保有するドライバーであれば、例えば、自宅から首都高速に乗り、10km先の目的地に到着するまでの道程は軽いドライブに入ります。
毎日のようにステアリングを握っているドライバーであれば、頭を抱えて難問に挑むかのように眉間にしわを寄せて運転している人は皆無なのです。
しかし、コンピューターとセンサー、カメラ、レーダーにとって、ドライバーの何気ない運転操作が神操作。
例えば、このようなシーン。
Aさんが駐車場に置いてある愛車に乗り込み、生活道路へ出ていきます。
【シーン1】

最初の交差点には、4方向全てに一時停止の標識が設置されています。各ドライバーは一時停止し、相手の車の動きやドライバーの顔の表情を確認しながら慎重に運転します。
4方向から車がやってきて一時停止した場合、各ドライバーは相手の微妙な動きやその時の空気を読み取ります。
場合によっては、相手のドライバーがジェスチャーで譲ってくれる時もあります。もちろん、自分から譲ることもあります。
ドライバー同士がコミュニケーションすることで、円滑な交通の流れが保たれます。
→ 4方向からほぼ同時に4台の車が一時停止した場合、各レベル5の自動運転車のシステムはどのように判断するのでしょうか?
例えば、4台の自動運転車が相互に通信しながら「じゃんけん」をして、勝った順で発進するのでしょうか?
【シーン2】

Aさんが片側1車線の生活道路を運転中、信号機の無い横断歩道が見えてきました。
その時、歩道に立っている人がAさんの視界に入ってきました。
その人の挙動から、道路を渡るかどうかの判断が微妙な場合、Aさんはアクセルペダルを戻し、減速しながら注意深く走行するでしょう。あるいは、横断歩道の手前で停止します。
もし、Aさんは人が明らかに道路を渡ろうとしていると読み取れば、Aさんは横断歩道の前で停止するはず。
→ 自動運転車(レベル5)はこの時、歩道に立つ人の挙動からどのように判断するのでしょうか?
自動運転車のシステムは、
・単に歩道でボーと立っている人
・歩道で道に迷っている人
・横断歩道を渡ろうとしている人
・横断歩道でしゃがんでいる人
以上の違いをどのように区別して判断するのでしょうか?
ステアリングを握っているリアルな人間でさえ、歩道に立っている人が横断歩道を渡ろうとしているのかどうか?判断が微妙な時があるのです。
道交法上、横断歩道を渡ろうとしている人がいれば、ドライバーは横断歩道の手前で一時停止しなければならないのです。
【シーン3】
Aさんは首都高のETCレーンを通過し、本線に合流します。首都高の加速レーンは短いため、注意深くドアミラーと肉眼で斜め後方を確認しながら、その時の本線の車列の流れを読み取ります。
本線が渋滞している場合、基本的に本線の車両が1台ずつ自車の前に合流してきた車を入れていきます。
→ この場合、本線の自動運転車(レベル5)と合流しようとしている自動運転車(レベル5)はそれぞれどのように判断するのでしょうか?
→ 本線の車列の流れが速く、合流するかどうか判断が微妙な場合、自動運転車(レベル5)はどのように判断するのでしょうか?
【シーン4】
目的地の手前に商店街があります。
商店街の道路は歩行者と自転車、バイク、車がミックス状態。いつ道路脇から子供や自転車が飛び出してくるか予測できない状況。
Aさんは20km/h以下で慎重に運転します。人や自転車、デリバリーのバイクが脇から飛び出してきても、急停止できるように細心の注意を払いながらの運転。
→ 自動運転車(レベル5)のシステムはこのようなシーンでどのように車をコントロールするのでしょうか?
システムが安全性を「0% or 100%」で考えるならば、「0%」と判断して身動きできなくなる可能性も考えられます。
【シーン5】
目的地の地下駐車場が満車状態。路上に空き待ちの車が4~5台、停車しているとします。
この場合、自動運転車(レベル5)はどのように判断するのでしょうか?自動運転車は空き待ち車両の最後尾に停車し、ただひたすら待ち続けるのでしょうか?
それとも、自動運転車が乗員に「近くの空き駐車場を探しますか?」と聞いてくるのでしょうか?
そのアナウンスのタイミングは待ち時間が1分、3分、5分経過したら発せられるのでしょうか?
千変万化する道路

雨や路面の落ち葉、泥
路面状況は天候によって刻一刻と変化します。
雨の降り始めは路面が滑りやすく、多くのドライバーは経験からこれを知っています。
荒れたアスファルト路面には水溜りができやすく、水溜りを通過するとハンドルが取られやすくなります。ドライバーはそのようなシーンで車速を落とす、あるいは、なるべく水溜りを避けて運転します。
山間部の峠道は落ち葉やコケ、雨によって流れてきた泥が路面を覆っていることがあり、ドライバーは当然、そのようなシーンでは車速を落とします。
→ タイヤは路面を覆っている泥やコケの上で非常に滑りやすく、制限速度以下でも、車体が横滑りすることがあります。自動運転車は、どのように路面状況を判断するのでしょうか?
そして、ベテランドライバーでさえ気を遣うのは冬季の雪道。
一口に雪道と言っても、路面のμは刻一刻と変化します。

新雪
太平洋側に積もる新雪と信州から北陸、東北、北海道の新雪を比較すると、雪質が明らかに異なります。
太平洋側に積もる雪は水分量が多く、重い雪。新雪であっても、太平洋側の雪は比較的滑りやすいのです。
そして、信州の一部や東北、北海道の雪はパウダースノーのため、スタッドレスタイヤがグリップしやすい傾向があります。もちろん、諸条件によって路面のμが異なります。
圧雪
圧雪であれば、比較的ドライブしやすいものの、それでも諸条件によって路面のμは変化します。特に、日陰の圧雪路面は表面がツルツル状態で滑りやすくなっている場合もあります。
シャーベット
シャーベット路面では、状況によっては50~60km/h程度でもハイドロプレーニング現象が発生し、スタッドレスタイヤがシャーベット路面の上で浮く瞬間があります。
その瞬間、ステアリング操作が不能となり、ブレーキペダルを踏んでも即、ABSが介入して車速がなかなか落ちないのです。
アイスバーン
路面が濡れているのか、それともアイスバーンなのか見分けが難しいシーンがあります。今をもってしても、スタッドレスタイヤが苦手とする路面はアイスバーン。
ベテランドライバーであっても神経を遣う雪道であるのに、天候やその他の諸条件によって千変万化する路面を自動運転車(レベル5)のシステムがどのように判断し、操作するのか、想像するだけでも困難を極めると言わざるを得ません。
雪道では当然、センターラインは存在しません。ガードレールは雪で覆われています。
ドライバーが登り坂の手前で「こりゃ~無理だ・・・」と判断し、タイヤチェーンを装着する場合もあります。
ドライバーは積雪状況によっては、これ以上、進むのは無理と判断し、Uターンして別の道を選択することもあります。
雪道において、カーナビが案内するルートは場合によって参考程度の情報となります。
雪道を運転するドライバーは複数のパラメーターから最適解を手探りで探しながら、安全かつ合理的な経路を探し続けます。
自動運転車(レベル5)が将来的にそのような芸当が可能なのか、現段階では何とも五里霧中なのではないでしょうか。
レベル3から難易度が一気に上昇
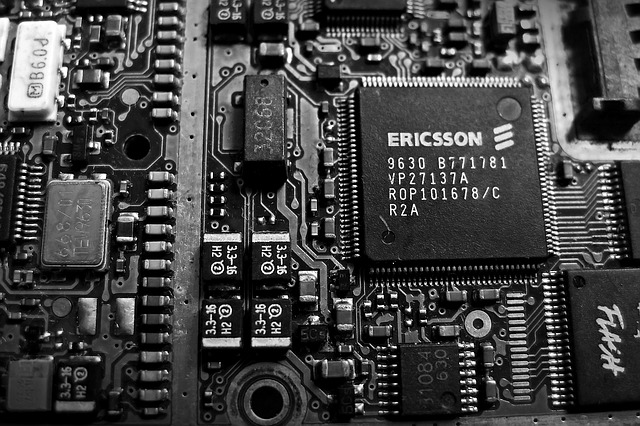
レベル3とは、
「限定的な条件下でシステムが加速、ステアリング操作、制動を行い、状況によってシステムがドライバーに運転をバトンタッチ要請する。」
という自動運転。
システムが加速、ステアリング操作、制動を行うためには高性能なコンピュータシステムが必要とされます。
自動車は人命を乗せて高速移動する乗り物である以上、万一を想定して設計する必要があります。
とすると、レベル5を目指して自動運転車の開発を進めると、コンピューターとセンサー、カメラ、レーダーシステムが重工長大化します。
当然、これらは車重の増加を招き、発熱、信頼性の確保、消費電力増による燃費悪化、コストアップ等の諸問題に直面することになります。
ただでさえ、自動車は熱と振動、水、湿度、砂埃の影響を受ける工業製品。複雑なコンピューターシステムは、これらの過酷な使用環境に強いとは言い難いのです。
レベル5は超難関
そこまで技術を投入して、自動運転車を開発するメリットがあるの?という考えもあるでしょう。
管理人があれこれと自動運転車について呟いてきたものの、管理人はレベル5の自動運転車は、まだ遠い未来の技術だと考えています。あるいは、完全な自動運転は不可能かもしれません。
ここで、
「東京都港区の新橋駅から江東区の豊洲駅を結ぶ”ゆりかもめ”は自動運転だから、車も自動運転が可能では?」
なんて、軽く考える方がいるかもしれません。
“ゆりかもめ”は中央指令所の運行管理者によって監視されています。運行管理者は運行表示板と各駅のモニターを見ながら、ゆりかもめの運行を管理しています。
よく考えてください。
高架式の線路を走る電車と一般公道を走る自動車を比較すると、運転の難易度が桁違いなのです。例えるならば、動物園の中の動物と野生動物くらいの生きている世界に違いがあるのです。
今後、レベル2や3の自動運転車は益々、増えていくことでしょう。しかし、その次のステップであるレベル4、レベル5となると、その壁は想像以上に高いと言えそうです。
【関連記事】





コメント
素人が書いたんだろうなぁという内容の記事ですね。
素人が当記事を読むと、「素人が書いたんだろうな~」と思うでしょう。